

奈良文化財研究所ホームページ「現地説明会」を更新しました。
奈良文化財研究所ホームページ「現地説明会」に1955年から2008年までの現地説明会、およそ300件の情報を追加いたしました。 現地説明会のページはこちら»https://www.nabunken.go.jp/fukyu/account.html 現地説明会で配布された資料も多数公開してお...
続きを読む
古代都市平城京の疫病対策
2020年5月 律令制度に基づく国家づくりが軌道にのり、平城京が国の中心として繁栄しつつあった天平7年(735)。天然痘とみられる疫病が、大宰府管内で流行し始めました。翌年には一旦、収束したともみられていますが、天平9年(737)4月に再度、大宰府管内で流行がはじまると、7月には平城京をはじめ畿内...
続きを読む
巡訪研究室(11)文化遺産部 景観研究室
はじめに 景観研究室では文化的景観の調査研究をおこなっています。文化的景観はその地域の歴史と風土に根ざした生活や生業の景観であり、地域の文化を総合的に捉える文化財です。代表的な例には、棚田や水郷などで知られる農山漁村の景観などがあります。 現在の日本社会では、少子高齢化・人口減少による地域社会...
続きを読む


桜の開花状況2020(満開)
平城宮跡の桜の開花状況をお知らせいたします。 先週に引き続き、全体的に満開を迎えております。 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 第二次大極殿付近 第二次大極殿付近 推定宮内省付近 推定宮内省付近 推定宮内省付近 第二次大極殿付近 第二次大極殿付近 第二次大極殿付近 東区朝堂院付近 東区朝堂院付...
続きを読む
奈良文化財研究所学報第50冊「平城宮発掘調査報告書XIII 内裏の調査Ⅱ 本文 図版」
奈良文化財研究所学報第50冊「平城宮発掘調査報告書XIII 内裏の調査Ⅱ 本文 図版」(THE NARA PALACE SITE EXCAVATION REPORT XIII)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 本文 https://sitereports.nabunken...
続きを読む
奈良文化財研究所学報第69冊「平城宮発掘調査報告ⅩⅤ 東院庭園地区の調査 本文編 図版編」
奈良文化財研究所学報第69冊「平城宮発掘調査報告ⅩⅤ 東院庭園地区の調査 本文編 図版編」(REPORT OF ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN THE EASTERN PALACE (TOIN) GARDEN OF THE HEIJO PALACE SITE, NA...
続きを読む
奈良文化財研究所学報第44冊「平城京左京三条二坊六坪発掘調査報告」
奈良文化財研究所学報第44冊「平城京左京三条二坊六坪発掘調査報告」(EXCAVATION REPORT ON THE SIXTH BLOCK IN SECOND WARD ON THIRD STREET,ANCIENT NARA CAPITAL)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。...
続きを読む
奈良文化財研究所学報第39冊「平城宮発掘調査報告Ⅹ 古墳時代Ⅰ」
奈良文化財研究所学報第39冊「平城宮発掘調査報告Ⅹ 古墳時代Ⅰ」(NARA (HEIJO) IMPERIAL PALACE SITE EXCAVATION REPORT X SURVEYS IN THE "KOFUN ER"-I)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https:/...
続きを読む
奈良文化財研究所学報第34冊「平城宮発掘調査報告Ⅸ 宮城門・大垣の調査」
奈良文化財研究所学報第34冊「平城宮発掘調査報告Ⅸ 宮城門・大垣の調査」(NARA HEIJO IMPERIAL PALACE SITE EXCAVATION REPORT IX SURVEYS IN AREAS OF OUTER GATES AND SURROUNDING WALLS)を電子公開し...
続きを読む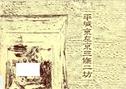
奈良文化財研究所学報第25冊「平城京左京三条二坊」
奈良文化財研究所学報第25冊「平城京左京三条二坊」(SURVEYS ON SITE OF 2ND WARD OF THIRD AVENUE OF THE EASTERN SECTOR, HEIJO CAPITAL (ANCIENT NARA))を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 ...
続きを読む
奈良文化財研究所学報第17冊「平城宮発掘調査報告Ⅳ官衙地域の調査2」
奈良文化財研究所学報第17冊「平城宮発掘調査報告Ⅳ官衙地域の調査2」(NARA IMPERIAL PALACE ARCHAEOLOGICAL SURVEYS CARRIED OUT DURING 1961-1963)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitere...
続きを読む
桜の開花状況2020(満開)
平城宮跡の桜の開花状況をお知らせいたします。 全体的に満開を迎えております。 平城宮跡資料館付近 第二次大極殿付近 第二次大極殿付近 第二次大極殿付近 第二次大極殿付近 推定宮内省付近 推定宮内省付近 推定宮内省付近 第二次大極殿付近 東区朝堂院付近 東区朝堂院付近 東区朝堂院付近 東区朝堂院付近 ...
続きを読む
新しい論集『奈文研論叢』創刊!
この度、奈良文化財研究所では『奈文研論叢』を創刊し、その第1号を刊行しました。 私たち奈文研の調査研究活動を支える原動力の1つは、専門分野を異にする所員の独創的な個人研究です。『奈文研論叢』は、奈文研所員がテーマや分量にとらわれることなく、個人研究の成果を自由に発表する場になります。この論集を通...
続きを読む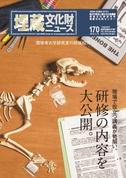
埋蔵文化財ニュースNo.136,138,163,170
埋蔵文化財ニュースNo.136,138,163,170(CAO NEWS Center for Archaeological Operations)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/maibunnew...
続きを読む
歴史を遺す写真の歴史
2020年4月 文化財を写真で記録し遺す。私の所属する写真室の現在の業務です。 写真を使って文化財を遺すことは実は古くからおこなわれています。近代写真技術が発明されたのは1830年代のダゲレオタイプ(いわゆる「銀板写真」)と言われています。写真機材が日本に渡来したのは1840年代の終わり頃、日本...
続きを読む
巡訪研究室(10)埋蔵文化財センター 環境考古学研究室
環境考古学研究室は、発掘調査で出土した動物の骨などから、過去の自然環境や食生活、生業など、人と自然がどのように関わりながら生きていたのか、その歴史を明らかにするための調査・研究をしています。 研究室の業務は、(1)出土資料の調査研究、(2)現生標本の収集・公開、(3)研修の実施、に大きく分けら...
続きを読む
奈良文化財研究所学報第95冊「日韓文化財論集Ⅲ」
奈良文化財研究所学報第95冊「日韓文化財論集Ⅲ」を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/63019 目次 ・日韓王陵級古墳における墳丘の特質と評価(青木 敬) ・高興野幕古墳からみた5世紀の対外交渉(権 宅章...
続きを読む
桜の開花状況2020(五分~七分咲き)
平城宮跡の桜の開花状況をお知らせいたします。 全体的に五分~七分咲きとなっております。 佐伯門付近の並木の一部の品種はすでに満開となっております。 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 推定宮内省付近 遺構展示館付近 ...
続きを読む