

奈良文化財研究所学報第77冊「日韓文化財論集Ⅰ」
奈良文化財研究所学報第77冊「日韓文化財論集Ⅰ」を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/62994 目次 ・日韓宮殿の設計思想について(内田 和伸) ・新羅王京の造営計画についての一考察(黄 仁鎬) ・庭園ス...
続きを読む
桜の開花状況2020(咲き始め)
平城宮跡の桜の開花状況をお知らせいたします。 連日、暖かな気候が続きましたので開花が進んでおります。 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 第二次大極殿付近 推定宮内省付近 推定宮内省付近 推定宮内省付近 推定宮内省付近背後の野鳥はモズ(百舌)(2017年1...
続きを読む
桜の開花状況2020(つぼみふくらむ)
平城宮跡の桜の開花状況をお知らせいたします。 日本気象協会発表の奈良市の予想開花日は、3月21日です。 来週中には開花の第一報をお届けできるかと思います。 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 第二次大極殿付近 推定宮...
続きを読む
3D Bone Atlas Databaseの更新(ウシ)
このたび、ウシの骨格図譜を刷新いたしました(2020年3月18日更新)。 大型哺乳類のために撮影作業は難航しましたが、これまで更新した動物たちとおなじように、大幅に部位データが増加され充実したものとなりました。遺跡から出土する牛骨への対応はもちろんのこと、それ以外の用途にもいろいろとご活用いただ...
続きを読む
いま長屋王家木簡を見直そう!
2020年3月 このコラムのタイトルにもなっている作寶樓の主、長屋王(676?-729)に関わる長屋王家木簡35,000点の発見(1988年)から、もう30年以上が経ちました。発掘調査によって住人を特定できた稀有の事例で、それも木簡の発見があればこそでした。 長屋王家木簡は、平城遷都直後の710...
続きを読む
奈良文化財研究所学報第87冊「日韓文化財論集Ⅱ」
奈良文化財研究所学報第87冊「日韓文化財論集Ⅱ」を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/63012 目次 ・7世紀の日本都城と百済・新羅王京(小澤 毅) ・新羅王京の整備における基準線と尺度(黄 仁鎬) ・日...
続きを読む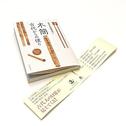
『木簡 古代からの便り』が刊行されました!
このたび奈良文化財研究所編『木簡 古代からの便り』が岩波書店から刊行されました(2020年2月26日初版)。 これは2018年4月7日から2019年3月30日まで、朝日新聞土曜版beに、「木簡の古都学」として47回にわたって連載したものに補訂を加え、若干の新稿とともに新たに編集したものです。 ...
続きを読む

巡訪研究室(9)都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)史料研究室
(2024年3月末まで) 【飛鳥時代の考古学―『日本書紀』『続日本紀』を掘る】 都城発掘調査部がおこなう発掘調査には、歴史学のスタッフが考古学の研究者とチームを組んで参加しています。歴史時代の考古学は、文字で記された史料が重要な手がかりとなるからです。藤原宮跡で検出した7基の柱穴が『続日本紀』にみえ...
続きを読む
梅便り2020(満開)
平城宮跡資料館東の梅林の開花状況をお知らせいたします。 全体的に満開となっております。日当たりの良い場所では、すでに散り始めている樹々もございます。 以下、平城宮跡資料館の東側梅林 撮影場所 クリックで拡大していただけます ...
続きを読む
奈良文化財研究所研究報告第24冊「デジタル技術による文化財情報の記録と利活用2」
奈良文化財研究所研究報告第24冊「デジタル技術による文化財情報の記録と利活用2」を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/69974 目次 凡 例 1.文化財情報のオープン化・ネットワーク化 [1]考古学に...
続きを読む
「発掘された平城 2019」ギャラリートーク②
2月21日(金)に、平城宮跡資料館にて開催しております「発掘された平城 2019」の関連イベントとして研究員によるギャラリートークを行いました。当日は天気も良く、多くのお客様にお越しいただきました。 第2回目となる今回は西大寺旧境内の発掘調査に関するお話です。 本調査では大型の掘立柱が発見され...
続きを読む
梅便り2020(五分~七分咲き)
平城宮跡資料館東の梅林の開花状況をお知らせいたします。 全体的に五分咲き~七分咲きです。 今年は記録的な暖冬の影響をうけて、開花も例年より二週間ほど早くなっております。 花の蜜を求めて飛び交う野鳥、メジロが「チーチーッ」と可愛い鳴き声を発しながら梅の木に集まってきています。 梅の花と野鳥に出会える早...
続きを読む
各地に潜む古代のことば ーブリ・ハマチ・イナダー
2020年2月 鹿児島県を旅行中、聞きなれない言葉を耳にしました。 「全部になりました。」 鹿児島地方では普通に使う言葉で、意味は「全部無くなった」とのこと。面白い表現だなあと感心してしまいました。 それからしばらくして、狂言を鑑賞してました。すると、空っぽになったことを、 「皆(みな)に...
続きを読む
全国遺跡報告総覧:類義語およびOCR誤認識用語検索機能の公開
以下の2つの機能を公開しました。より網羅的なテキスト全文検索を目指します。 キーワード検索時に類義語およびOCR誤認識用語(表記ゆれ)の登録がある用語の場合、検索結果にチェックボックスが表示されます。 〇類義語を含めた検索専門用語の使い方は、専門家の認識や研究史に基づきます。ただし研究成果を社会に普...
続きを読む
「発掘された平城 2019」ギャラリートーク①
平城宮跡資料館では、2月1日(土)より「発掘された平城 2019」と題して2018年度の発掘調査の成果をご紹介しています。 今回は、平城宮東院地区、平城宮東区朝堂院、西大寺旧境内、左京二条二坊十五坪の発掘調査と楊梅宮に関する最新の研究成果を取り上げました。 会期期間中は研究員によるギャラリート...
続きを読む
梅便り2020(つぼみ膨らむ~三分咲き)
平城宮跡内の梅林の開花状況をお知らせいたします。 東院庭園は三分咲き、平城宮跡資料館の東側はつぼみが膨らみ一部開花しております。 2月4日に二十四節気の一つ「立春」を迎え、朝晩の冷え込みは厳しいながらも季節は着実に春へとむかっています。 降り注ぐ柔らかな日差しに、梅の香りをのせて吹き渡る風に少しずつ...
続きを読む
巡訪研究室(8)企画調整部 国際遺跡研究室
国際遺跡研究室では、カンボジアやカザフスタンにおける国際共同事業を推進するとともに、奈文研が行っている様々な海外調査・研究・国際交流に関しての支援・調整・情報収集を行っています。また、ユネスコ・アジア文化センター奈良事務所(ACCU)の研修活動の共催・協力や、東京文化財研究所の行う国際共同研究の...
続きを読む
バクテリアがつくる顔料
2020年2月 日々の生活の中で、道路の側溝や水路の排水口に、褐色の沈殿や鉄サビ色の泥が流れたような痕跡を目にしたことはないでしょうか。例えば、図1の写真は、私が毎日通勤ルートで見かけてきたものです。 この褐色の堆積こそ、バクテリアがつくる顔料「パイプ状ベンガラ」の原料です。 パイプ状ベンガラは...
続きを読む
全国遺跡報告総覧:発掘調査報告書総目録 大阪府・兵庫県・島根県・高知県編の書誌情報を全国遺跡報告総覧に登録
2018年・2019年に公開した発掘調査報告書総目録の書誌情報を全国遺跡報告総覧に登録しました。 大阪府 発行機関一覧https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/list/27 兵庫県 発行機関一覧https://sitereports.nabunken.go.jp/...
続きを読む