

![西トップ遺跡通信20(2020年7月20日)[Western Prasat Top 20]](https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/assets_c/2020/07/wpt20_1-thumb-126xauto-16653.jpg)
西トップ遺跡通信20(2020年7月20日)[Western Prasat Top 20]
西トップ遺跡に見られる動物意匠 アンコール遺跡群の中に位置する西トップ遺跡の建造物は、砂岩という比較的柔らかい石材でできています。砂岩には様々な装飾が施されており、訪れる人の目を楽しませてくれます。西トップ遺跡は仏教寺院として機能していたと考えられているだけあり、遺跡内では仏像など多くの仏教的な図...
続きを読む

歴史や文化財の魅力を伝えたい!
2020年7月 考古学専門ではないからこそ、わかりやすく伝えられる 飛鳥資料館や奈良文化材研究所といえば、考古学のイメージが強いかと思いますが、考古学以外にも様々な分野の研究者が協力して調査・研究を進めています。 私は飛鳥資料館で学芸業務をしていますが、専攻は考古学ではなく「文化遺産マネジメント...
続きを読む
埋蔵文化財ニュースNo.166,172,173,175,176,177,178,181
埋蔵文化財ニュースNo.166,172,173,175,176,177,178,181(CAO NEWS Center for Archaeological Operations)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publi...
続きを読む
奈文研ニュースNo.76、No.77
「奈文研ニュースNo.76、No.77」(NABUNKEN NEWS No.76,No.77)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 ■No.76 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/71453 目次 ・ベトナム・カイベー集落調査に対するティエ...
続きを読む
平成30年度遺跡整備・活用研究集会報告書
「史跡等の保存活用計画-歴史の重層性と価値の多様性- 平成30年度 遺跡整備・活用研究集会報告書―」を学術情報リポジトリで公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 http://hdl.handle.net/11177/7728 目次 凡 例 はじめに 史跡等の保存活用計画-歴史の重層性...
続きを読む
東アジア考古学論叢-日中共同研究論文集-
「東アジア考古学論叢-日中共同研究論文集-」を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/71168 目次 慕容鮮卑関連墳墓の立地に関する基本的データの作成と省察 北票・喇嘛洞墓地出土「人面飾金具」考 喇嘛洞出土の...
続きを読む
オンラインデータベースの翻訳
2020年7月 奈文研のホームページでは、『木簡庫』や『全国遺跡報告総覧』など、数多くのオンラインデータベースが公開されています。これらのデータベースの一部は日本語以外の言語にも対応しています。今回はオンラインデータベースをどのように多言語化対応させるのか見てみましょう。 データベースは基本的に...
続きを読む
巡訪研究室(13)飛鳥資料館 学芸室
飛鳥資料館は、飛鳥地域の歴史や文化を紹介する展示施設として、1975年(昭和50)に開館しました。展示室は3室からなり、一階の第1展示室では飛鳥地域の歴史をテーマ別に展示し、第2展示室では山田寺東回廊の建物を中心に山田寺の出土品(重要文化財)を紹介しています。地下の特別展示室では、年に4回ほど、...
続きを読む
古代東北アジアにおける金工品の生産・流通構造に関する考古学的研究
2014年度~2017年度科学研究費(学術研究助成金(若手研究B) )研究成果報告書「古代東北アジアにおける金工品の生産・流通構造に関する考古学的研究」を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/71203 目次...
続きを読む![西トップ遺跡通信19(2020年6月24日)[Western Prasat Top 19]](https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/assets_c/2020/06/wpt19_1-thumb-126xauto-16607.jpg)
西トップ遺跡通信19(2020年6月24日)[Western Prasat Top 19]
仏像台座編 2019年秋から2020年2月にかけて中央祠堂の解体・修復調査に伴って、中央祠堂東正面の調査を順次おこないました。中央祠堂東正面には「仏教テラス」とも呼ばれる細長いテラス状の壇が延びています(写真1)。このテラス上に中央祠堂の基壇から続く台座状の遺構があります(写真2)。この遺構の修復...
続きを読む![西トップ遺跡通信18(2020年6月17日)[Western Prasat Top 18]](https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/assets_c/2020/06/wpt18_1-thumb-126xauto-16605.jpg)
西トップ遺跡通信18(2020年6月17日)[Western Prasat Top 18]
中央祠堂ラテライト基壇編 西トップ遺跡の調査修復事業では、2015年末に南祠堂再構築、2017年末に北祠堂再構築をそれぞれ完了し、2018年1月より中央祠堂の解体修復調査をおこなっています。2018年1月中に、崩壊が進んでいた中央祠堂屋蓋部の解体と仮組作業を終え、順次躯体部の解体へと進みました。2...
続きを読む
「生」の食品と加工した食品
2020年6月 「生(なま)」の対義語は「加工」です。でも、古代において煮たり焼いたり蒸したり漬けたりした食品をぜんぶひっくるめて「加工」食品とは言いません。荷札・付札木簡などを眺めていると調理した食品にはその加工法が記されていることが多いように思います。 アワビはさまざまな加工をして都にもたら...
続きを読む![西トップ遺跡通信17(2020年6月10日)[Western Prasat Top 17]](https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/assets_c/2020/06/wpt17_1-thumb-126xauto-16601.jpg)
西トップ遺跡通信17(2020年6月10日)[Western Prasat Top 17]
レンガ積遺構編 西トップ遺跡では、2016年1月から北祠堂の解体調査を進めました。解体調査の経過についてはこれまでの西トップ通信でお伝えしてきたところです。実はその後、北祠堂においてアンコール遺跡では初めてとなる大きな発見がありました。それが、北祠堂下成基壇地下から発見されたレンガ積遺構です。 ...
続きを読む
埋蔵文化財ニュースNo.180
埋蔵文化財ニュースNo.180(CAO NEWS Centre for Archaeological Operations)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/70959 N...
続きを読む
巡訪研究室(12)都城発掘調査部(平城地区)考古第三研究室
(2024年3月末まで) ・瓦礫の山 瓦礫(がれき)とは建物の崩れた残骸のことを意味します。平城宮や平城京の寺院を発掘すると、写真にあるように多量の瓦が出土します。これらは、当時の人々が使えなくなって捨てたゴミです。私たちはゴミを研究していると自負!しています。さて、何ゆえに瓦を専門に扱う研究室が...
続きを読む
ヤリガンナ木屑の行方
2020年6月 みなさんは、昨年10月におこなわれた第一次大極殿院南門復原整備工事の特別公開には足を運ばれましたか。私も足を運び、職人さんが木材を削るところを見学し、またVRシアターでは完成した南門の姿を空中から楽しみました。 中でも、宮大工実演のコーナーでは、ヤリガンナという大工道具で木材を削...
続きを読む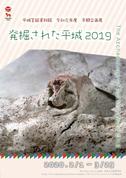
平城宮跡資料館 令和元年度冬期企画展「発掘された平城2019」リーフレット
平城宮跡資料館令和元年度冬期企画展「発掘された平城2019」リーフレット を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/70925 ...
続きを読む![西トップ遺跡通信16(2020年5月25日)[Western Prasat Top 16]](https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/assets_c/2020/05/wpt_1-thumb-126xauto-16579.jpg)
西トップ遺跡通信16(2020年5月25日)[Western Prasat Top 16]
2019年に私たち奈良文化財研究所のカンボジア事業が25周年の区切りを迎えたことを受け、2019年12月2日、修復作業が大詰めを迎えている西トップ遺跡現地で、「奈良文化財研究所カンボジア事業25周年式典」を開催いたしました(写真1)。 写真1 奈良文化財研究所は、内戦終結直後の1993年に、カン...
続きを読む