
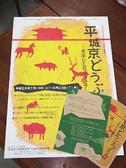

ただいま準備中です!
みなさん、はじめまして。 この夏、奈良文化財研究所・平城宮跡資料館では、 「平城京どうぶつえん-天平びとのアニマルアート-」と題した企画展を開催予定です。 このブログは、この「平城京どうぶつえん」の特設ブログで、 バタバタとした準備の様子から、展示に隠された小ネタ紹介、ギ...
続きを読む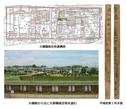

かたおもいの歌と土器
2013年7月 思い遣る すべの知らねば かたもひの 底にそ我は 恋ひなりにける 土垸の中に注せり 上は万葉集巻四 707番の歌で、粟田女娘子(あわためのいらつめ)が若き日の大伴家持に贈った歌です。家持への「片思い」を「かたもひ」という土製のうつわに掛け、その伝わらぬ思いを吐露したもので、いわ...
続きを読む
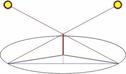


飛鳥寺と奈文研-終わらない調査研究と保存
2013年5月 いまは田園風景がひろがる飛鳥の地。その飛鳥の核といってもよい飛鳥寺は、わが国で最初の本格的な仏教寺院とされています。『日本書紀』には崇峻元年(588)、百済から僧、技術者たちとともに仏舎利がもたらされ、「始めて法興寺を作る。」と記されています。この法興寺が、飛鳥寺のことです。各地で...
続きを読む
平城宮跡ギャラリー 2013年3月
資料館東 (2013年3月6日) 東院庭園 (2013年3月6日) 東院庭園 (2013年3月6日) 資料館東 (2013年3月12日) 桜並木 (2013年3月12日) 資料館東の梅 (2013年3月12日) 資料館東 (2013年3月22日) 色づく (2013年3月22日) つぼみ (201...
続きを読む





![西トップ遺跡通信7(2012年6月14日) [Western Prasat Top 7]](https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/assets_c/2021/04/20120614_1A-thumb-126xauto-26414.jpg)
西トップ遺跡通信7(2012年6月14日) [Western Prasat Top 7]
しばらく途絶えていました西トップ通信ですが、新年度になって新たな調査が始まり、研究員が頻繁に現地入りするようになりました。6月は考古班の第14次調査と6月6・7日に開催された国際技術委員会出席のために、6月1日から調査団が現地入りしました。西トップ遺跡では上成基壇の解体が進んでおり、下成基壇の...
続きを読む
今、世はイクメンの時代。
2012年5月 テレビや雑誌には、育児を積極的に「楽しむ」父親達が盛んに登場します。こうなると、イクメンならざる父親とて、育児への「協力」程度はせざるを得ないわけで、かくして私も、有無を言わさず子育ての渦中へと巻き込まれることとなった次第であります。そんな経験のおかげで、今まで気にもとめていなかっ...
続きを読む
平城宮跡ギャラリー 2012年4月
もう咲いている!? (2012年4月2日) 嵐の前!! (2012年4月3日) 一輪咲く (2012年4月3日) 嵐ニモマケズ (2012年4月4日) 資料館出口前の桜 (2012年4月4日) 春の陽気 (2012年4月5日) 資料館出口前の桜 (2012年4月5日) 風雨耐え・・ (2012年4...
続きを読む![西トップ遺跡通信6(2012年4月2日) [Western Prasat Top 6]](https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/assets_c/2021/04/20120402_1A-thumb-126xauto-26416.jpg)
西トップ遺跡通信6(2012年4月2日) [Western Prasat Top 6]
現地から報告が届いたのでアップします。中成基壇の解体が始まりました。中成基壇は6段で構成され、四方に階段が取り付きます(写真1)。1段1段、石を外しながら、内部の土を取り除く作業が続いています(写真2)。一番上の石を外したところです(写真3)。基壇外周には砂岩を横に使い、その内側に縦に砂岩平石...
続きを読む
平城宮跡ギャラリー 2012年3月
さざんか (2012年) 梅 (2012年3月13日) つくし (2012年3月13日) 鷺が餌とり (2012年3月21日) つぼみ (2012年3月21日) つぼみふくらむ (2012年3月26日) つぼみ色づく (2012年3月27日) あとちょっと!! (2012年3月31日) もう少しで...
続きを読む