

全国遺跡報告総覧:大阪府松原市の文化財調査報告書を公開開始
大阪府松原市の文化財調査報告書を公開しています。 大和川・今池遺跡等の調査報告書があります。 ・難波大道 http://sitereports.nabunken.go.jp/17317 ・大和川・今池遺跡 http://sitereports.nabun...
続きを読む
全国遺跡報告総覧:大阪府羽曳野市の文化財調査報告書を公開開始
大阪府羽曳野市の文化財調査報告書を公開しています。 古市遺跡群等の調査報告書があります。 ・古市遺跡群 http://sitereports.nabunken.go.jp/17333 >>大阪府羽曳野市 - 報告書一覧 http://site...
続きを読む
平城宮跡東方官衙の檜扇(ひおうぎ)
2016年9月 平城宮の東側には奈良時代の役所の区画が南北に連なっていた地区があります。平城宮跡東方官衙地区と呼んでいるこの範囲のうち中央よりやや南の区画を2008年12月から2009年2月にかけて発掘調査したところ、大きな楕円形の土坑が見つかりました。この土坑は東西約11m、南北約7mの大きさ...
続きを読む
(147)平城京北辺の巨大古墳群
雄大な「盾列」残る一端 奈良盆地の北側を限る平城山(ならやま)は、標高90~100メートルほどのなだらかな丘陵です。その南斜面には、4世紀後半から5世紀中頃にかけて、数多くの古墳が築かれました。佐紀盾列(さきたたなみ)古墳群と呼ばれる全国有数の古墳群で、墳丘の長さが200メートルを超える巨大な前...
続きを読む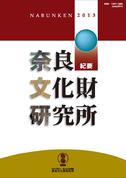
奈良文化財研究所紀要2013
『奈良文化財研究所紀要2013』(Bulletin of National Research Institute for Cultural Properties, Nara)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publi...
続きを読む
東院庭園観月会開催いたしました
9月17日夕刻、恒例となりました東院庭園での秋の催し、東院庭園観月会を開催いたしました。 本年は満月にあわせての開催となり、あいにくの曇り空にも関わらず、時折姿を見せる満月を背景に、奈良時代の東院庭園で行われた宴の様子を再現し、約150名のお客様には、当時の食事と飲み物を合わせて楽しんでい...
続きを読む
(146)平城京と大和三道
都市計画の基準線 みなさんは奈良の都、平城京の場所がどのようにして決められたか、知っていますか? 何も考えずに決められたわけではありませんよ? 奈良盆地には、平城京がつくられる前から、東西方向と南北方向に走る複数の直線道路がありました。現在の国道のルーツともいうべき道路です。平城京はこうし...
続きを読む

講演会 英国発!グローバル考古学のご報告
去る、平成28年9月3日(土)に講演会「英国発!グローバル考古学」を当研究所平城宮跡資料館講堂において開催しました。 松村所長による挨拶の後、英国のセインズベリー日本藝術研究所サイモン・ケイナー考古・遺産学センター長による「加速化する日英の文化財交流」、ケンブリッジ大学ミルヤーナ・ラディヴォイ...
続きを読む

全国遺跡報告総覧:鹿児島県天城町の文化財調査報告書を公開開始
鹿児島県天城町の文化財調査報告書を公開しています。 戸森の線刻画調査報告書などがあります。 ・戸森の線刻画調査報告書 http://sitereports.nabunken.go.jp/ja/17114 ・中組遺跡 http://sitereports.nabunken.g...
続きを読む
全国遺跡報告総覧:鹿児島県瀬戸内町の文化財調査報告書を公開
鹿児島県瀬戸内町の文化財調査報告書を公開しています。 詳細分布調査報告書などがあります。 ・瀬戸内町遺跡詳細分布調査報告書 http://sitereports.nabunken.go.jp/17075 >>瀬戸内町 - 報告書一覧 http://siter...
続きを読む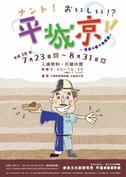
平成28年度平城宮跡資料館夏のこども展示「ナント!おいしい!?平城京!!-奈良の都の食事情-」リーフレット
平成28年度平城宮跡資料館夏のこども展示「ナント!おいしい!?平城京!!-奈良の都の食事情-」リーフレット を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/18361 今年で4回目となる、小学校親子向けの夏の企画展...
続きを読む
文化的景観研究集会(第8回)の開催 その3:エクスカーション編
文化的景観研究集会(第8回)のエクスカーションは、重要文化的景観の選定を目指した取組をおこなっている京都市北区中川北山町を対象に、「中川村おこしの会」の全面的なご協力のもと実施することができました。 中川集落は、磨き丸太や垂木生産をおこなう北山林業の中心地です。水田は一枚もなく、山は畑のように...
続きを読む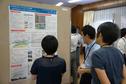
文化的景観研究集会(第8回)の開催 その2:ポスターセッション編
文化的景観研究集会(第8回)では、昨年度に引き続き、ポスターセッションも開催しました。今年度は以下の計18題の発表がありました。 【学術研究部門】 □A-1 文化的景観の価値の把握と共有におけるフェノロジーカレンダーの有用性~北海道美瑛町を対象として~/麻生美希(九州大学)、真板...
続きを読む
文化的景観研究集会(第8回)の開催 その1:シンポジウム編
景観研究室では、2016年7月30日〜31日にかけて、文化的景観研究集会(第8回)「地域のみかたとしての文化的景観」を開催しました。 今年度の文化的景観研究集会は、2016年3月に刊行した『地域のみかた 文化的景観学のすすめ』という本を片手に、各地域や各学術分野において、文化的景観がどのような...
続きを読む
(145)平城宮最大の瓦工場
ひしめく窯 新技術開発 平城宮の北側にある奈良山丘陵。現在は住宅街となっていますが、奈良時代にはここに、平城宮・京の瓦を生産する瓦工場が集中していました。なかでも丘陵南西にある中山瓦窯(がよう)は、最大の瓦工場で、平城宮の大極殿や東区朝堂院などの重要な建物の瓦を生産していたことがわかっています。...
続きを読む
全国遺跡報告総覧:英語自動検索機能公開のお知らせ
全国遺跡報告総覧の英語検索画面にて、英語の考古学用語を検索ワードとした場合、日本語の考古学用語に自動変換したうえで、類語を含めて検索します。 本機能は、「Tarnslate Free Word」をonにした場合、有効になります。システム内部に日英対訳の考古学用語(約5000語)と日...
続きを読む
(144)写真が遺す歴史
37万枚の学術情報 写真による正確でわかりやすい記録は、文化財の調査研究に欠かせません。奈文研は文化財の調査研究にあたり、多くの写真を撮影し、学術情報として保存してきました。その数は37万枚にもおよびます。 奈文研による飛鳥地域の発掘調査は、今からちょうど60年前、飛鳥寺跡から始まりました。...
続きを読む
「興福寺 第1期境内整備事業にともなう発掘調査概報Ⅰ」他
「興福寺 第1期境内整備事業にともなう発掘調査概報Ⅰ」他 を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 興福寺 第1期境内整備事業にともなう発掘調査概報Ⅰ(1999) 興福寺 第1期境内整備事業にともなう発掘調査概報Ⅱ(2000) 西隆寺跡発掘調査報告書(2001) 興福寺 第...
続きを読む