

ハエがつないだ日韓交流
2019年7月 ポンテギという韓国の食べ物をご存知でしょうか?ポンテギとは、韓国語でさなぎを意味する単語ですが、一般的には、蚕のさなぎを醤油などで甘辛く煮たものを指し、ある時はマッコリのつまみとして、ある時は食べ歩きのおやつとして屋台で目にする、韓国ではお馴染みの食べ物です。しかし、とにかく見た目...
続きを読む
第124回公開講演会の開催
去る、令和元年6月15日(土)に第124回公開講演会を当研究所平城宮跡資料館講堂において開催しました。 松村所長による挨拶の後、前川研究員による「第一次大極殿院南門の復原」と題してのトピック講演があり、引き続き松田研究員による「出土木製品の恒久的な保存と一時的な保管」、村田研究員による「防災・減...
続きを読む
全国遺跡報告総覧:都道府県別の発掘調査報告書総目録 大阪府編の公開
これまで戦前を含め発掘調査報告書の発行数は不明であり、十数万~二十万冊とも言われてきました。奈良文化財研究所(以下、奈文研)では、実数を確定するため、全国の発掘調査報告書の総目録を作成しています。大阪府編が完成しましたので、公開します。 URL(全国遺跡報告総覧):発掘調査報告書総目録 大阪府編 h...
続きを読む
「時をこえて」掘りおこされた埴輪
2019年6月 木々の新緑がまぶしい平城宮跡は、遠足シーズンもあって小学生でにぎわう季節を迎えています。その平城宮の正門、朱雀門の前に、昨年3月に開館した「平城宮いざない館」があります。奈良時代を体感し、その舞台となった平城宮跡に親しんでいただくための、ガイダンス施設です。 平城宮いざない館の...
続きを読む
平城宮跡大極殿院地区の発掘調査(平城第612次調査)の現地説明会のご報告
令和元年6月7日(金)、平城宮跡大極殿院地区の発掘調査(平城第612次調査)の現地説明会を開催しました。 当日は180名の方にご参加いただきました。 発表資料はこちらです。 >>電子公開ページ 発掘担当者からのコメント:都城発掘調査部 主任研究員 桑田 訓也 雨の降りしきる中、予想を上回る多くの方...
続きを読む
全国遺跡報告総覧:全国の遺跡や文化財に関するイベント情報検索機能公開のお知らせ
このたび、2016年9月から公開しているイベント情報の検索機能を改善しました。 種別(展覧会、講演会、現地説明会、その他)、開催日、開催地、フリーワードなどから、関心に合わせて各地の遺跡や文化財に関するイベント情報を検索しやすくなっています。 また、全国遺跡報告総覧に登録された報告書に表示される「内...
続きを読む
「骨ものがたり-環境考古学研究室のお仕事」の舞台裏
2019年6月 現在、飛鳥資料館では、春期特別展「骨ものがたり-環境考古学研究室のお仕事」が開催されています。(4月23日~6月30日) 環境考古学とは、遺跡から出土する動植物遺存体(骨や種子など)の調査を通して、昔の生活環境や食生活、生業など、人と自然がどのように関わりながら生きていたのか、そ...
続きを読む

モンゴルの兵馬俑 "Shoroon Bumbagar"
2019年5月 皆さんが「兵馬俑」という言葉を聞いたとき何を連想されるでしょうか? おそらく、多くの人は中国の秦の始皇帝陵をすぐに思い浮かべるのではないかと思います。確かに、始皇帝陵の兵馬俑は世界的にも有名で、質・量ともに群を抜いています。しかし、兵馬俑は始皇帝陵だけで発見されているわけではありませ...
続きを読む
ヒラドツツジの開花状況(満開)
平城宮跡は目にも鮮やかな新緑に彩られ、爽やかな風が吹き渡る季節を迎えています。 暦の上で夏が始まる日とされている二十四節気の一つ「立夏」を迎え、毎年この季節には、色とりどりのヒラドツツジ(平戸躑躅)が見頃となります。 平城宮跡の随所でご覧いただけますので、散策に是非お越しください。 平城宮跡資...
続きを読む
埋蔵文化財ニュースNo.171,174
埋蔵文化財ニュースNo.171,174(CAO NEWS Centre for Archaeological Operations)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/maibunnews.html ・...
続きを読む
特集展示「埋(うず)もれた大宮びとの横顔―薬・まじない・庄園の木簡」の展示替えをおこないました
現在、藤原宮跡資料室玄関ホールで開催している特集展示「埋(うず)もれた大宮びとの横顔―薬・まじない・庄園の木簡」は、4月18日から後期の木簡展示をおこなっています。 後期にご紹介する2点の木簡は、いずれも大型の帳簿で、弘仁元年から2年にかけての庄園の収支簿と、都へ米を進上した記録木簡です。藤原宮...
続きを読む
「奈文研ニュースNo.72」
「奈文研ニュースNo.72」(NABUNKEN NEWS No.72)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/54410 目次 ・調査研究の舞台裏を展示する(小沼 美結・西田 紀子) ・藤原宮外周帯の調査(飛...
続きを読む
全国遺跡報告総覧:都道府県別の発掘調査報告書総目録 新潟県編の公開
これまで戦前を含め発掘調査報告書の発行数は不明であり、十数万~二十万冊とも言われてきました。奈良文化財研究所(以下、奈文研)では、実数を確定するため、全国の発掘調査報告書の総目録を作成しています。新潟県編が完成しましたので、公開します。 URL(全国遺跡報告総覧):発掘調査報告書総目録 新潟県編 h...
続きを読む

桜の開花状況2019(満開)
平城宮跡の桜の開花状況をお知らせいたします。 今まさに満開を迎えた平城宮跡にぜひお越しください。 平城宮跡資料館付近 第一次大極殿を望む 第二次大極殿付近 第二次大極殿付近 第二次大極殿付近 礎石 第二次大極殿付近 第二次大極殿付近 東区朝堂院付近 東区朝堂院付近から第一次大極殿を望む 東区朝堂院付...
続きを読む
藤原宮跡資料室 特集展示「埋(うず)もれた大宮びとの横顔―薬・まじない・庄園の木簡」
奈良文化財研究所では、2019年1月に『藤原宮木簡四』を刊行しました。本展示では、『藤原宮木簡四』に掲載した木簡から、藤原宮の時代に用いられた薬の木簡、まじないの符号を記した呪符、藤原宮の跡地に営まれた庄園で平安時代初期に作成された大型の帳簿など、計21点を、2期に分けてご紹介します。 普段、目...
続きを読む
全国遺跡報告総覧:欧州考古学情報基盤ARIADNE Plusへの奈良文化財研究所の参画について
1、ARIADNE Plus参画の概要 ARIADNEは、多国間での考古学情報を統合し、相互連携によって多くの人が情報にアクセスしやすくするシステムの構築、コミュニティの組成に取り組んでいるEUの事業です。 第二期計画であるARIADNE Plusでは、ヨーロッパ各国に加え、日本・アメリカ・アルゼン...
続きを読む
桜の開花状況2019(五分~八分咲き)
平城宮跡の桜の開花状況をお知らせいたします。 今週は強い寒気の影響をうけ、季節外れの寒さに見舞われました。 一転して、今週末はうららかな陽気に包まれ、絶好のお花見日和になりそうです。 春本番を迎えた平城宮跡にぜひお越しください。 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 平城宮跡資料館付近 第二次大極...
続きを読む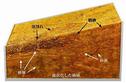
遺跡に刻まれた災害の爪痕
2019年4月 先日(3/8)、平城宮跡資料館で開催されている「発掘された平城2017・2018」(2019/2/2~3/31)のギャラリートークで、平城京跡で発見された地震の痕跡についてお話しさせていただきました。平城宮の正門・朱雀門の周辺から出土した人形や、法華寺旧境内から出土した井戸枠の磚...
続きを読む