

文化的景観保存計画の概要(Ⅱ)
「文化的景観資料集成 第2集 文化的景観保存計画の概要(Ⅱ)」を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/org/bunka/land-material.html 表紙 ...
続きを読む
(105)平城宮と百万塔
5年半こつこつ大事業 天平宝字8年(764年)9月、ときの権力者、藤原仲麻呂が反乱をおこしました。この反乱をしずめた称徳天皇は、乱で亡くなった人々を悼み、また国家の安泰を願って、百万基もの木製の三重小塔を作らせました。これが百万塔です。完成後に奈良やその周辺の10のお寺に10万基ずつ安置されまし...
続きを読む
文化的景観研究集会(第7回)開催のお知らせ
景観研究室では、2015年11月28日(土)〜29日(日)に文化的景観研究集会(第7回)「営みの基盤 –生態学からの文化的景観再考−」を開催いたします。 今回の研究集会では、人々の営みの基盤としての自然環境に着目し、それらをいかにして一連のものとして...
続きを読む
全国遺跡報告総覧によくあるご質問を追加
よくあるご質問を集めたページを公開しました。 一般利用の方と自治体担当者の方向けです。 ・登録されている報告書に都道府県ごとに偏りがあるのはなぜですか。 ・古い報告書が登録されていないようですがなぜですか。 ・以前あった遺跡資料リポジトリとの違いはなんですか。 ・自機関で発行した報告書...
続きを読む
(104)古代のカレンダー
巻物 板に書き写し みなさん、ゴールデンウィークはいかがでしたか? 今年は、秋にも大型連休がありますね。 過去のできごとを振り返るにも、今後の予定を立てるにも、あるいは、今日の日付の確認にも。カレンダーは、私たちの生活に欠かせません。 奈良の都においても、カレンダーは必需品でした。 ...
続きを読む
全国遺跡報告総覧に奈良文化財研究所の刊行物を登録開始
全国遺跡報告総覧に奈良文化財研究所の刊行物を登録開始しました。 http://sitereports.nabunken.go.jp/ja/list/29/J84604 ...
続きを読む
(103)習書の文字
上達目指し繰り返し 漢字練習が今週末の宿題、という人はいませんか? 古代の役人も皆さんに負けないぐらい、一生懸命漢字の練習をしていました。 以前、「難波津の歌」での手習いをご紹介しました。今回は同じ文字の「繰り返し練習」の紹介です。 写真の木簡では、ぎっしりと、同じような漢字を繰り返し練習し...
続きを読む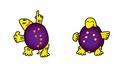

SNS連携ボタンを設置しました
全国遺跡報告総覧にはてなブックマーク、Google+、twitter、FacebookとのSNS連携ボタンを設置しました。 http://sitereports.nabunken.go.jp/ja ...
続きを読む

(102)大極殿 なぜ二つある?
政務と儀式 使い分け 大和西大寺駅から近鉄奈良駅へ向かう電車に揺られていると、左手の遠方に第一次大極殿が見えてきます。この建物は、2010年の平城遷都1300年を記念して奈良時代の姿に復元された平城宮を代表する建物です。 でも、「第一次」とはどういう意味でしょうか。「第二次」よりも前のものと...
続きを読む
「奈文研ニュースNo.57」
「奈文研ニュースNo.57」(NABUNKEN NEWS No.57)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/nabunkennews.html 目次 ・飛鳥資料館 開館40周年を迎えて(石橋 茂登) ・檜...
続きを読む

アンコール遺跡群・西トップ遺跡ニューズレター10号・11号
「カンボジア王国アンコール遺跡群・西トップ寺院遺跡保全プロジェクト ニューズレター 10号・11号」を学術情報リポジトリで公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/angkor-newsletter.html ...
続きを読む
自然を使いこなした都市の営み
2015年7月 銀閣寺の銀沙灘、詩仙堂や南禅寺塔頭の枯山水庭園など、中世から近世にかけて京都でつくられた庭園には、「白川砂」と呼ばれる、白くきらめく砂が多用されてきました。一方、明治末頃から昭和初期にかけて、琵琶湖疏水からの水を利用して南禅寺界隈につくられた無鄰庵、碧雲荘、對龍山荘といった別邸群...
続きを読む
奈文研ニュースNo.57「埋蔵文化財の発掘調査報告書全文データベース「全国遺跡報告総覧」の公開」
奈文研ニュースNo.57に「埋蔵文化財の発掘調査報告書全文データベース「全国遺跡報告総覧」の公開」を掲載しました。 奈文研ニュースNo.57 ...
続きを読む

文化的景観保存計画の概要(Ⅰ)
「文化的景観資料集成 第1集 文化的景観保存計画の概要(Ⅰ)」を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/org/bunka/land-material.html 表紙 ...
続きを読む
埋蔵文化財ニュースNo.161
埋蔵文化財ニュースNo.161(CAO NEWS Centre for Archaeological Operations)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/maibunnews.html No.16...
続きを読む
WEBで発掘調査報告書を読める「全国遺跡報告総覧」公開のお知らせ
2015年6月25日、全国遺跡報告総覧を公開しました。 http://sitereports.nabunken.go.jp/ja ■概要 ・埋蔵文化財の発掘調査報告書を全文電子化、"電子書庫" ・約 14000 冊が登録 ・キーワード検索や地域ごとの情報を入手可能 ・奈良文化財研究所がクラウドプラッ...
続きを読む