

体験!!文化財写真(1)
―かたい?ねむい?文化財写真の合格・不合格― 『文化財を撮る』の展示には、 文化財写真の仕事を体感してもらうコーナーがあります。 例えば、飛鳥の甍を撮影した写真。 陰影のはっきりした写真は、一見、格好良く見えます。 ところが、この写真は文化財の記録としては不合格。 ...
続きを読む
東大寺正倉院宝物と中央アジア
2016年5月 東大寺の正倉院宝物といえば、美しく装飾された楽器や色鮮やかな錦などが思い浮かびますが、刀や弓矢など武器も伝わっています。ここでご紹介したいのは金銀鈿荘唐大刀という儀仗用の大刀です(図1)。正倉院宝物の台帳である国家珍寶帳には、唐大刀13口と唐様大刀6口の記載があります。唐大...
続きを読む
『文化財を撮る』のオススメ!!この一枚(3)
-昭和27年度の岡寺仁王門- 飛鳥は新緑が目にまぶしい季節。でも、あえて今回のオススメはモノクロの写真です。 奈文研の文化財写真、第一号は岡寺の仁王門の写真でした。 戦後の混乱を経て、文化財の研究や保存にむけた体制が整えられつつあった時期。 仁王門も、軸部...
続きを読む
『文化財を撮る』の裏話(3)
―ポスター写真に見る遊び心― 現在開催中の特別展『文化財を撮る―写真が遺す歴史』。 ポスターやチラシに大きく写るクラシカルなカメラが目を引きます。 このカメラは60年以上前につくられたドイツの「Leica Ⅲf」というカメラで、 奈良文化財研究所が文化財調査の記録写真の撮...
続きを読む
『文化財を撮る』の裏話(2)
―写真のボリュームに驚いてください!― 現在開催中の春期特別展では、図録も販売しております。 この図録を編集するにあたり、奈良文化財研究所が今までに撮影してきた写真で、 特に飛鳥・藤原地域に関する写真台帳を見直し、聞き取り調査も行いました。 みなさんに「おもしろい!」「興...
続きを読む
全国遺跡報告総覧:システムメンテナンス実施のお知らせ
2016年5月21日(土)0:00 - 24:00の間、システムメンテナンスを実施します。そのため不定期にシステムを利用できない可能性があります。 ご迷惑おかけします。 >>全国遺跡報告総覧...
続きを読む
『文化財を撮る』のオススメ!!この一枚(2)
-昭和45年の藤原宮跡- 展示された写真の中から、担当者のオススメ一枚を紹介するコーナー、 今回は昭和45年(1970)の藤原宮跡の写真を紹介します。 これは、奈文研が藤原宮跡の発掘調査を本格的に始めた時期の写真です。 写真の中央には、発掘調査の作業風景が...
続きを読む
『文化財を撮る』の裏話(1)
―飛鳥資料館の古い招待券発見!― ただいま開催中の特別展『文化財を撮る―写真が遺す歴史』では、 飛鳥資料館の歴代ポスターの一部も展示しています。 懐かしいポスターもご覧いただけます。 そして本日、飛鳥資料館の平成3年度秋期特別展『飛鳥の源流』の招待券が偶然...
続きを読む
(135)平城京のお墓(2)
官人と庶民 古墳再利用 川に遺棄も 前回は平城京に暮らす人々のうち、天皇や貴族・官人が亡くなった後、平城京の周辺の丘陵や山中に葬られたことを紹介しました。 官人の中には、遠い故郷に葬られた人もいたようです。因幡国(現在の鳥取県)出身の伊福吉部徳足比売(いふきべのとこたりひめ)は、和銅元年(7...
続きを読む
『文化財を撮る』のオススメ!!この一枚(1)
-川原寺跡の塔心礎- 飛鳥資料館では4月26日から春期特別展を開催しております。 展示された写真の中から、担当者のオススメの一枚を紹介します。 これは、天智天皇がつくったとされる、川原寺跡の発掘調査でみつかった塔の心礎の写真です。 心礎とは、塔の中心に立つ...
続きを読む
飛鳥資料館の春期特別展『文化財を撮る―写真が遺す歴史―』がはじまりました
法隆寺金堂壁画写真をはじめとする重要文化財の写真資料と、 飛鳥寺跡の発掘調査現場の写真など、 奈文研が文化財調査の現場で撮影した写真を展示しています。 さらに、今回の展示は見るだけではありません。 ホンモノの出土品を置いた写真スタジオや、 時間による影の出方のうつりかわ...
続きを読む
(134)平城京のお墓(1)
天皇と貴族 周辺の丘や山中に埋葬 奈良時代、平城京には5~10万人もの人々が暮らしていました。彼らが亡くなった後、たくさんのお墓が必要になったはずですが、一体どこに葬られたのでしょうか? 当時の法律では平城京内での埋葬は固く禁止されていました。このため、お墓は京外に造られました。 ...
続きを読む
![西トップ遺跡通信13(2016年5月2日) [Western Prasat Top 13]](https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/assets_c/2016/11/13-1-thumb-126xauto-14808.jpg)
西トップ遺跡通信13(2016年5月2日) [Western Prasat Top 13]
北祠堂下成基壇の解体 これまでのところ北祠堂の解体作業は順調に進んでいますが、南祠堂と大きく異なる点が新たに発見されました。かつて南祠堂では、中央祠堂の南階段を残したまま基壇を構築していたため、私たちが基壇内を発掘したところ、きれいな状態の中央祠堂南階段が発見されました(写真1)。ところが...
続きを読む

奈良文化財研究所研究報告第17冊(2016)「藤原宮跡出土馬の研究」
奈良文化財研究所研究報告第17冊(2016)「藤原宮跡出土馬の研究」 を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/hokoku.html 目次 第1章 藤原宮跡から出土した動物遺存体 第2章 事前調査 第...
続きを読む
(133)古代の地盤改良
穴掘り 土砂で固める 皆さんが生活する家。家の下の地盤が軟らかいと、家の重さを支え切れずに家が沈み込んで傾くおそれがあります。 そこで、しっかりとした地盤につくりかえる地盤改良の工事をおこなう場合があります。この地盤改良工事、実は千数百年前からおこなわれていました。 特に、瓦葺(ぶ)き屋...
続きを読む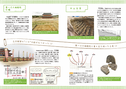
平城宮跡資料館ミニ展示「発掘速報展平城2015」 リーフレット
平城宮跡資料館ミニ展示「発掘速報展平城2015」 第Ⅰ期・第Ⅱ期リーフレット を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 第Ⅰ期 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/16681 第Ⅱ期 https://sitereports.nabunke...
続きを読む
「奈文研ニュースNo.60」
「奈文研ニュースNo.60」(NABUNKEN NEWS No.60)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/16824 目次 ・ミャンマーでの研修事業(森本 晋) ・...
続きを読む
足元に小さな春を見つける
4月も半ばを迎え、日中は汗ばむぐらいの陽気の日が多くなりましたね。 宮跡内の動植物たちの成長はめまぐるしく、草花たちは太陽を仰ぐように元気に咲きほこっています。 カーペット状に一面に咲くムラサキサギゴケ、眩しい黄色はタンポポ、清楚な白はスミレ、ぽんぽん花開くのはシロツメグサ。こういった...
続きを読む