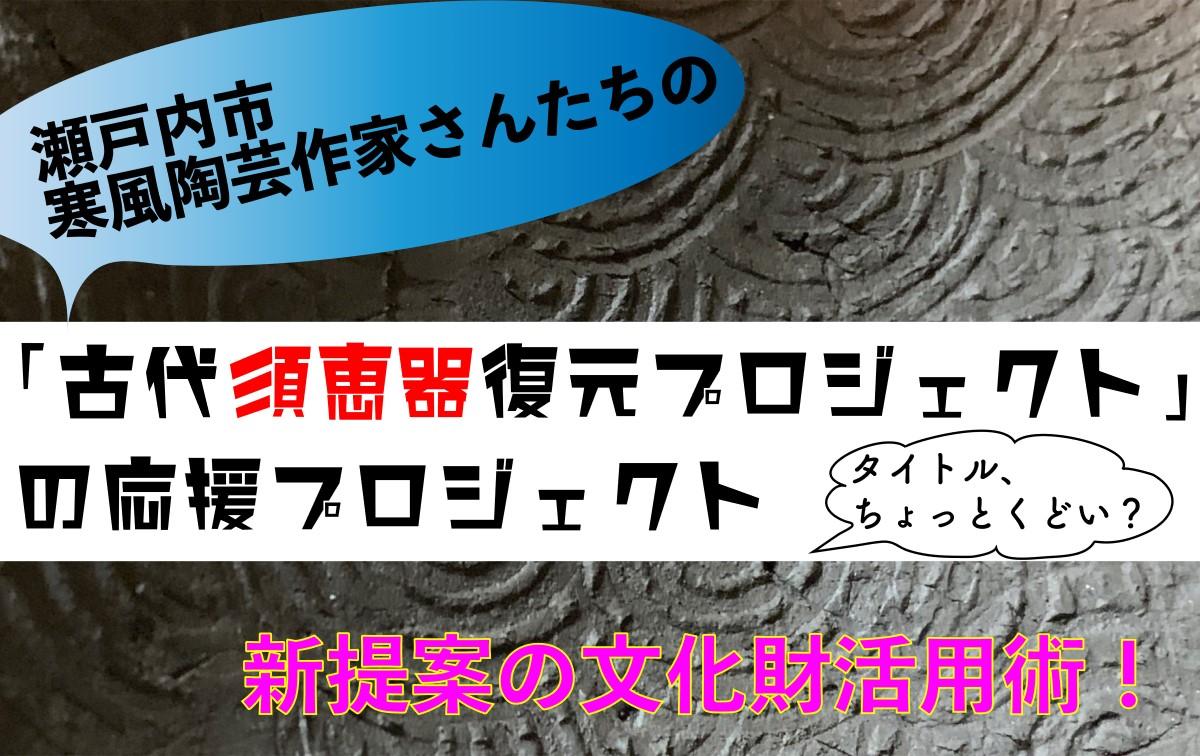平城宮いざない館で夏期企画展「須恵器をつくる―古代と現代をつなぐ陶の工の物語―」を開催します。<7月12日(土)から8月31日(日)まで>
 【画像1】古代の須恵器(寒風窯、飛鳥・藤原地域出土)
【画像1】古代の須恵器(寒風窯、飛鳥・藤原地域出土)
須恵器と「陶の工」
「須恵器」とは土師器とともに古代日本を代表する焼き物の一つで、高い温度で焼かれた硬い焼き物です【画像1】。須恵器はロクロを使って成形し、窯を使って焼成するという、古墳時代に朝鮮半島から伝わった技術により製作されました。そのため、須恵器を作るためには専門的な技術をもつ工人「陶の工」の存在が不可欠でした。
また、各地で生産された須恵器は、税や交易品として都に運ばれていました。平安時代の『延喜式』には、税として須恵器を納めた国(調納国)の名前が複数挙げられています。しかし、各地から都に納められた須恵器はどれか、古代の須恵器の生産や流通の実態についてはまだ分からないことがたくさんあり、都や生産地から出土した須恵器に残された「陶の工」の技術やクセを見抜くための細やかな観察と研究が重要になります。

【画像2】寒風古窯跡群(寒風陶芸会館提供)
寒風古窯跡と古代の都
さて、調納国のひとつにあたる備前国(現在の岡山県東部)に、寒風古窯跡群という窯跡があります【画像2】。岡山県瀬戸内市牛窓にあるこの窯跡は、生涯にわたり須恵器研究を続けた時實黙水さんが戦前に発見した須恵器窯です。その後、岡山県教育委員会や瀬戸内市教育委員会によって発掘調査がおこなわれ、7世紀の飛鳥時代を中心に約100年にわたって須恵器を生産していたことがわかっています。

【画像3】列点で装飾された須恵器蓋(寒風窯・飛鳥地域出土)
近年、寒風窯の「陶の工」が製作した製品が、飛鳥の宮都まで運ばれていたことがあきらかになってきました【画像3】。飛鳥の川原寺下層から出土した列点で装飾された特徴的な蓋とそっくりな須恵器が寒風窯から出土していることがわかりました。また、奥山廃寺から出土した鴟尾が寒風窯と同じ特徴をもつということが、自然科学分析の結果からもわかってきました。
今回の企画展では、寒風窯と飛鳥地域から出土した資料を並べて展示しますので、これらを見比べながら寒風窯の「陶の工」と都のつながりをご覧いただきたいと思います。
現代の「陶の工」
この古代の寒風窯の「陶の工」たちに魅了された現代陶芸作家の方々がいます。
彼らは寒風古窯跡群の近くに窯を築き、当時からあまり変わらない景観と環境のなかで、古代の須恵器製作技術を再現しようと、日々製作活動に取り組んでいます。
実は私たち奈文研研究員も、古代の須恵器製作技術について調べる過程で現代の「陶の工」である寒風の陶芸作家さんたちと出会い、その技術を実際に見せていただくことで遺物の観察から想定した作り方の検証をお願いするなど、交流を続け多くのことを学んでいました。詳しくはなぶんけんチャンネル「古代須恵器復元プロジェクト」をご覧ください。【画像4】
【画像4】なぶんけんチャンネル「古代須恵器復元プロジェクト」
今回の展示では、古代の「陶の工」の技に刺激を受けた作家さん達の作品も展示いたします。
古代と現代の「陶の工」の共演となる、今回の「須恵器をつくる」展では、出土遺物や作品の背景にある「陶の工の物語」をぜひご覧いただきたいと思います。
※内容を一部修正しました(7月16日)
(展示公開活用研究室 小田裕樹)