概要
写真室について
写真室では研究所の実施する調査研究をはじめとした文化財調査に必要不可欠な写真記録について、デジタルでの撮影・記録の管理や保存の実務を担当しています。
また、全国の文化財担当諸機関における写真記録の品質向上に向けて技術開発や研修での技術普及の業務を実施しています。
文化財における写真の役割
文化財調査研究において写真の役割とは対象の情報を詳細に記録し、かつその記録を後世にまで活用できるように保存していくことです。たとえば埋蔵文化財の分野において土の中から発掘される遺物の中には急激な酸化等により取り上げた時点では原形を保っていたものが時間の経過と友に変色・変形し、最悪の場合出土品そのものが失われてしまうこともあります。また発掘調査が終了すれば遺構は埋め戻され、二度と見ることが出来ない場合が多く、撮影した写真が調査結果を検討し成果をあきらかにするための重要な手段となります。そのためにあらゆる角度や高さの選択肢から最適な撮影アングルを選び、文化財の情報を自然な形で引き出して記録します。

ヘリコプターを使い高い高度からの撮影

世界遺産平城宮跡を空から記録する

世界遺産平城宮跡を空から記録する

低い角度からの撮影が効果的な場合もある
これらの画像を後世に活用するためにはそれぞれの詳細な情報を記録できるように撮影することが重要です。そのために撮影時点で最良の機材を選択しつつ、できる限り最高の画質をもって的確に撮影すること、またいつでもその情報を引き出すことが出来るように管理・保存していくことが重要です。
私たち写真室では文化財の撮影にはこれまで4×5inchや8×10inchといった大判フィルム写真を使ってきました。現在ではこれらを高精細デジタル撮影に置き換え、より正しい色調や高精細な記録で記録できるようにハイエンドデジタルカメラを使用し、並行して全国の文化財担当者のみなさんが最低限の機材で最大限の記録を残せるような技術も検討し続けています。

ハイエンドデジタルでの出土遺物撮影

斜め上からの撮影で立体遺物を明瞭に記録
文化財写真技師
「カメラマン」って、華やかな職業のイメージが強いと感じる方が多いと思います。でも文化財のカメラマンは文化財を写真として記録に残すことを続けている、どちらかと言うと地味な作業の積み重ねをしています。
奈文研が属する国立文化財機構の施設のうち、東京・京都・奈良・九州の各国立博物館と東京・奈良の文化財研究所には、写真技術職員が配置されています。 奈文研では企画調整部に写真室があり常勤職員3名とスタッフ2名が配置されており、研究所の扱う幅広い文化財の写真記録を担う部屋として写真室が存在しています。
様々な写真
遺跡の撮影
遺跡の高所撮影の多くは、組み立て式の足場から撮影します。このほか、15m・20mクラスの高所作業車を使用したり、ヘリコプターからの航空撮影もおこないます。 発掘される遺跡の土の色は地味で色目が少ないので、写真で表現することは大変難しく、撮影には苦労します。遺跡の立体感や質感を出すためには、撮影時間や撮影方向を考えながら撮影にのぞみます。

足場を使った遺跡撮影風景
遺物の撮影
遺跡から出土した遺物は立面や俯瞰で撮影します。
遺物写真は、遺物の細部が観察でき、「とばず、つぶれず」、立体感や質感が失われないようにしなければなりません。 そのため様々な工夫をしながら撮影しています。

遺物の撮影風景
特殊撮影
木簡の撮影
木簡の撮影は、文字を判読しやすくするために、赤フィルターをかけたり、ライティングを工夫して撮影します。
また、肉眼では見えない文字は赤外線撮影用に改造したデジタルスチルカメラで撮影します。この撮影方法は私たち写真室が考案しましたが、その利便性から今では全国の調査機関や博物館などで採用されています。

遺物の撮影風景
フォトマップ
フォトマップとは、計測対象に出来るだけ正対して撮影をおこない、その撮影データを解析・合成することにより、計測対象に非接触で正確な図面と写真画像を得る技術です。キトラ古墳や高松塚古墳でその成果を発揮しました。

遺物の撮影風景
文化財写真技術研究会
文化財写真技術研究会とは
本会は文化財の調査研究に関する写真技術全般の向上を図り、その研究・開発・普及を目的とする研究会です。 活動には下記の3本の柱があり、上記の目的を達成するために精力的に活動しています。
1, 文化財全般の写真技術に関する情報の整理・公開・普及
2, 研究集会の開催
3, 文化財写真技術の向上を目的とした講習会の開催
※平成21年7月より、埋蔵文化財写真技術研究会は「文化財写真技術研究会」へ名称を変更しました。
文化財写真技術研究会
開催期日 : 平成22年7月2日(金)~3日(土) 終了しました。
開催場所 : 奈良文化財研究所 平城宮跡資料館講堂
文化財写真技術研究会 会誌
文化財写真研究 vol.1
| ・巻頭言 埋文写真の理想と現実 |
坂井秀弥 |
| ・特集 デジタルフォトへの第一歩 写真業務用カラーマネージメントの現状 デジタル入稿とカラーマネージメント |
玉内公一 岩本康平 宮内康弘 |
| ・基礎講座 あらためて始めるデジタルフォト デジタル部会 |
穆 啓文 |
| ・SUPER SHOT 喇嘛洞出土文物撮影に思う 文化財(建造物)修理における写真記録 |
石綿吾朗 井上直夫 |
| ・Technical Report 俯瞰撮影 |
菊池慈人 |
| ・Photo Essay 伊藤コレクション |
杉浦秀昭 |
| ・Letter Box 第一回文化財写真セミナー in北海道 |
菊池慈人 |
| ・Gallery 牛嶋茂退職記念『USHIJIMA写真館』 FOOTWORK |
|
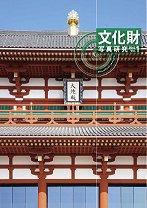 |
発行日 : 2010年7月2日 発行 編集発行: 文化財写真技術研究会 頒 価 : 3,500円 |
Gallery
Gallery

本薬師寺(橿原市)

香具山(橿原市)

平城宮パノラマ


