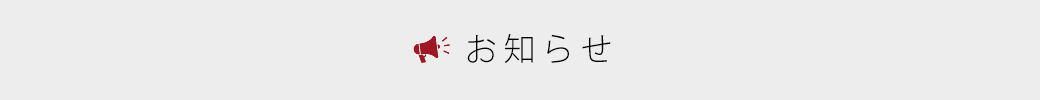
【飛鳥のくらし】田植えの風景と田の神
6月初めから中ごろに飛鳥を歩くと田植えの光景を目にすることができます(写真1)。平地の比較的大きな田んぼでは田植え機を使いますが、傾斜地に営まれる小区画の田んぼでは現在も手植えでおこなわれます。
飛鳥での手植えの風景は、室町時代から上演が確認できる『飛鳥川』という能にも見ることができます。「飛鳥川、岸田の早苗(さなえ)とりどりの、袖もみどりの景色かな。」、「山ほととぎす声そへて、うたふ田歌もなほしげし。」と、主演の早乙女が田植歌を歌いながら手植えしていく情景は何ともさわやかです。同時に、この早乙女は田の神に仕える巫女でもあり、生き別れとなっていた子どもと神の徳によって再会を果たします。
田植えと田の神の関わりは飛鳥坐(あすかにいます)神社のおんだ祭でも垣間見ることができます。この祭りは子孫繫栄と五穀豊穣を祈る祭りです。有名な夫婦和合の神事の前には、田起こしから田植えまでを演じる御田植(おたうえ)神事がおこなわれます。神事の終わりには稲に見立てられた苗松(なえまつ)が参拝者の頭上に投げられます(写真2)。この松は苗代田(なわしろだ)への水の取り入れ口近くに季節の草花やお札などとともに立てられます(写真3)。苗松は舞い降りる田の神の依り代(よりしろ)としての意味合いがあるのかもしれません。
飛鳥の諸集落では、田植えが完了した後に神前で食事をともにする、さなぶり(早苗ぶり)という行事をおこなってきました。一般に、さなぶりは田植え時に降臨していた田の神を送る意味合いがあるとされます。だとすると、田の神はおんだ祭りで配られた苗松に舞い降り、田植えを見届けてから帰っていくということになるのでしょうか。苗松が置かれた水田は、くらしの風景であり、祈りの風景でもあるのです。
第14回写真コンテストのテーマは「飛鳥のくらし」です。風景や物、行事、作業など、「飛鳥のくらし」にまつわる写真を広く募集します。6月30日(金)まで、みなさまのご応募をお待ちしております。応募方法等の詳細はこちら。
参考文献 飛鳥民俗調査会編(1987)『飛鳥の民俗』飛鳥保存財団

写真1 第10回写真コンテスト「飛鳥の木」 正二位飛鳥古墳右大臣「悠久」柳敏明様

写真2 第11回写真コンテスト「飛鳥の祭」 正二位飛鳥祭右大臣「御田植神事」山本弘様
写真3 苗代田に立てられた苗松と草花
2023年05月31日(水曜日)


 ページトップ
ページトップ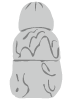

 ご利用案内・交通アクセス
ご利用案内・交通アクセス