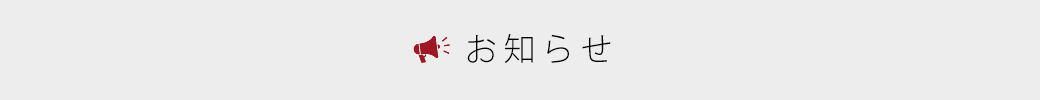
6月10日(金)は「時の記念日」です
6月10日は「時の記念日」です。
1920年に東京教育博物館(現在の国立科学博物館)で開催された、時間に関する展覧会がきっかけで制定されました。『日本書紀』天智天皇10年4月25日に漏刻(水時計)を設置して時を知らせ始めた、という記載があり、これが現在の暦に当てはめると671年6月10日になるため、この日となりました。
ただし、初めて漏刻の記述が登場するのはそれより11年前の、斉明天皇6年(660)5月の記事です。このときに設置された漏刻が明日香村にある水落遺跡と考えられています。飛鳥は日本における時間の歴史と深い関わりがあるのです。
水落遺跡からは、「地中梁工法」という変わった構造を持つ建物や、高度な技術で作られた配水用の銅管など、特殊なものが数多く見つかっています。飛鳥資料館では漏刻の原寸大模型などを製作して、こうした情報をわかりやすく展示しています。
水落遺跡の話をはじめとして、飛鳥についてわかりやすく解説した本が、奈文研編集の『飛鳥むかしむかし』(朝日新聞出版、2016年、2分冊)です。こちらは一般の書店でも購入できますので、一度手に取ってご覧ください。
『飛鳥むかしむかし 飛鳥誕生編』
『飛鳥むかしむかし 国づくり編』
2022年06月09日(木曜日)
ブログ


 ページトップ
ページトップ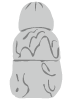

 ご利用案内・交通アクセス
ご利用案内・交通アクセス